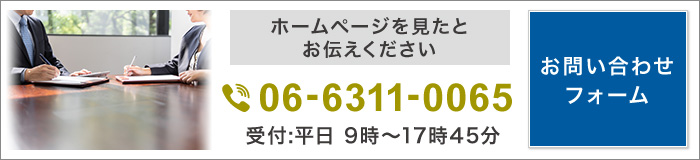我が国における労働トラブルは、究極的には話し合いの上和解による解決がなされることがほとんどで、労働審判や訴訟になっても和解によって解決することが多いのです。
もっとも、そこに至る経緯はさまざまですし、和解できない場合も少なくはなく、その場合は徹底的に争い判決を求めざるをえません。
ただ、判決に至るにしても、次に述べるように他の手続を吟味し、何がもっとも事案の性質に合うのかを検討し、よりよい解決を目指しましょう。
このページの目次
1 示談和解による場合
労働者と会社の直接の交渉による場合や、双方または一方に弁護士が就いて交渉を行い、和解をする場合がこれにあたります。
示談交渉の仕方は自由で、労働組合との交渉でもない限り、面会しての交渉の必要もありません。電話だけで交渉し、和解書を取り交わして終わる場合から、当時者が何度も面談して和解に至る場合も様々です。
2 労働委員会による手続
労働関係調整法に基づき、中央労働委員会によるあっせんなどの手続を行う場合があります。
労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が3名選任されます。3名は、一人は公益側(学識経験者等)、一人は労働者側(労働組合役員等)、一人は使用者側(会社経営者等)から選任され、公平なスタンスで話が進みます。また、申立の費用がかからないのも利点です。納得いかなければ、和解に応じないことも可能で、応じなくてもペナルティーはありません。
労働紛争の分野ではともすればマイナーな手続ですが、専門的知識を持った第三者が介入してくれること、また、会社側からの申立てもできること、あっせんの対象となる紛争の幅が広いことなど、意外といえば失礼ですが、使いやすい制度です。
3 労働審判
交渉で解決が難しいような事案で、裁判所による解決を求める方法として、労働審判という制度があります。
労働審判は、裁判官と労働審判員(労働者側、使用者側1名ずつ)によって構成される委員会によって行われる裁判手続ですが、最大の特徴は訴訟にはないスピード感です。
労働審判の申立ての多くは労働者から起こされますので、会社側は、労働審判申立書と呼出状をはじめに受け取って知ります。呼出状には第一回期日の日が指定されています(申立てをされた日から40日以内とされているので、おおよそ呼出状を受領してから1か月程度の日)。
しかし、この第一回期日までに、会社側は自社の主張を整理して詳細に答弁書で述べ、証拠も提出しなければなりません。
裁判所も申立人(多くは労働者)の申立書と、第一回期日までに出される相手方(多くは会社)の答弁書で心証を持ってしまいます。
そのため、申立てを起こされた側にとっては、反論をする時間が限られるのに、しっかり反論しなければならず、非常にタイトなスケジュールになります。
もっとも、労働審判は、裁判所の心証を素早く感じ取り、短期で解決を図るには優れた制度といえます。
4 訴訟
上記のいずれの方法でも解決が難しいような場合、訴訟の提起がなされることがあります。
訴訟は、通常の民事訴訟の一種として扱われ、だいたい1か月に1回のペースで裁判が開かれます。1回の裁判で一方の主張を記載した書面が提出されますので、2か月に1回ペースでこちら側の主張を述べてゆくことになります。
そのため、労働事件が訴訟となった場合、第一審の判決が下されるまで、どんなに早くても半年以上はかかることになり、判決まで通常1年はかかります。
訴訟は、民事の分野では最終的な紛争解決手段ですので、裁判官が下した判決というのは勝訴にせよ敗訴にせよ重みがあります。日本は三審制をとっていますが、地方裁判所の判断が高等裁判所で覆ることは多くなく、高等裁判所の判断が最高裁で覆ることは極めて稀なことです。
したがって、判決というのは一度出されてしまうと、覆すのが難しいことを前提に、訴訟を進める必要があります。また、リスク回避の観点から訴訟になった場合でも和解の検討は行うべきです。