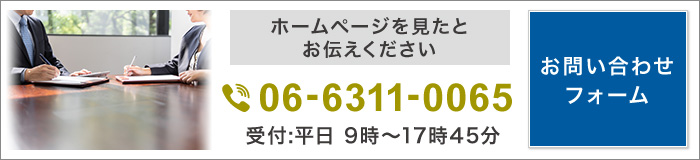このページの目次
1 円満退社でも残業代請求される

「円満退社したと思った従業員から、残業代請求が届いた」というご相談をよくお聞きします。
近年、我が国では年功序列、終身雇用の制度は崩れつつあります。若年の方を中心に転職も盛んにおこなわれており、人々の労働観はドライになっているように感じます。そのため、「円満退社でも、正当な権利は主張したい。残業代は払ってもらいたい」と考えている方は増えているようです。
「円満退社だったし、話せばわかってくれるのではないか」と考えると思うのは早計です。
2 残業代請求を無視するとどうなる?時効は?
(1)法律改正で時効が延びました
従業員からの残業代請求を無視した場合、従業員が諦めてしまって、時効にかかることがこれまではありました。
これは残業代がそこまで大きな金額にならず、弁護士費用や訴訟の費用や手間に比べて割に合わないことが背景にありました。
残業代の時効は最近までは「2年」でした。しかし、2020年4月1日から民法、労働基準法が改正されました。新しい消滅時効期間は、改正以後に支払期日が到来する賃金については、「3年」とされました。つまり請求できる残業代は概ね1,5倍になったというわけです。
また、この3年というのは当面の間の経過措置で、将来的には「5年」になる見込みです。
これまで、残業代請求の事件は、労働者からの請求額が多くて200万円程度、和解による解決金額が100万円から150万円になることが多かったのです。これは月約20万円の賃金をもらっている従業員が1か月に40時間サービス残業した場合、約5万円の未払い賃金が発生し、その2年分が120万円となることからイメージできると思います。
しかし、2020年の法律改正で将来的には5年分遡って残業代請求が可能となると、会社への請求は上記の2,5倍、500万円程度になりかねませんし、和解額も300万円程度になることが予想されます。
これからの残業代請求は高額化し、会社にとってシビアな結論になることも予想されますし、従業員の側でも諦めてしまうことも少なくなると思われ、弁護士を用いて請求をしてくること、労働裁判を提起することも増えてくるでしょう。
とすれば、放置、無視は、会社にとってデメリットしかありません。早期に弁護士に相談し、解決を目指しましょう。
(2)いわゆる36協定は無関係
このような残業代請求を受けたとき、「ウチの会社は36協定を締結しているから問題ない」と考えるのは間違いです。
たしかに、労働基準法36条は、「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定しており、時間外労働をさせることができるとしています。
しかし、いわゆる36協定を締結した場合は、残業させてもよいということになっているにすぎず、割増賃金の問題はこれとは別問題で、割増賃金は支払わなければなりません。
この割増賃金は次のように定められています。
- 通常の時間外割増賃金 1,25倍
- 休日労働の割増賃金 1,35倍
- 深夜労働の割増賃金 1,25倍
- 時間外かつ深夜 1,5倍
- 休日かつ深夜 1,6倍
なお、②休日労働の割増賃金は、そもそも「時間外」ですので、休日かつ時間外の割増賃金というものはありません。
3 固定残業制度は危険がいっぱい
残業については毎月固定で支給する固定残業代制度を導入しておられる企業もよくお聞きします。固定残業代制度が残業代圧縮の秘策ともてはやされたこともありました。
しかし、会社が定めた固定残業代が、固定残業代として認められるには、次の要件が必要です。
- 固定残業代とそれを除いた基本給の額を明確に定めましょう。
例)基本給として20万円、固定残業代として4万円という表示がこれにあたります。 - 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法を定めましょう。
例)固定残業代:20時間分として、40,000円
なお、この固定残業代の単価は、少なくとも基本給の1,25倍の単価になっている必要があります。 - 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うことを明らかにしておきましょう。
すなわち、上記の例で、固定残業代制度を導入していた場合でも、20時間を超えた残業を行ったのなら、超過分を支払わなければなりませんし、休日労働をした場合は別途支払わなければなりません。
固定残業代制度は、残業代計算の手間を一定程度軽減してくれる制度ではありますが、法律上は、残業代を安くできる制度ではないことを意識するべきです。
むしろ、不完全な固定残業代制度を導入した場合、固定残業代部分も基本給に組み込まれてしまい、残業代計算の基礎にされてしまう恐れがあります。こうなると割増賃金額は大幅に上昇し、企業の首を絞めることになります。固定残業代のつもりで「営業手当」などとしてお給料を支払っていると、予想もしない請求を受けることがあります。
4 残業代が紛争になりやすいケース
①手持ち時間が長い会社は要注意
手待ち時間が長い業務については残業代が問題になりやすいといえます。
例えば、運輸業の場合、客先で荷物積み込みを待つ時間、ドライバーがトラックの中で食事をとったり、トラック周辺でたばこを吸ったりするような時間まで労働時間に含まれるのかという問題です。
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令に服している時間」であり、これの対概念として考えうる「休憩時間」には、休憩時間自由使用の原則があることに注目して考えていくべきでしょう。
上記の例では、トラック運転手にとって、待ち時間にトラックを離れて、自由に過ごすことが可能であったかなどが検討されることになります。
一般的にドライバーが配達先、集配所などで、会社のトラックから自由に離れて、休憩ができるとは考えられません。
そうすると、会社側の休憩時間の主張は認められず、例えば、客先で荷積みをまっていたような時間がすべて労働時間になって残業代を求められてしまいます。
②営業職
外回りの営業職には営業手当が支給されており、その分、残業は認めないとする会社を見かけます。これは、労働基準法第38条の2の事業場外みなし労働時間を意識しておられるのだと思います。
しかし、この規定が当然に適用されるかは疑問があります。
例えば、何人かのグループで社外の仕事をしている場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合や、携帯電話によって随時会社の指示を受けながら会社外で労働している場合などは、「みなし労働時間」は使えません。
その他にも、会社外で行う業務に通常必要な時間が、所定の労働時間を超える場合は、労使協定の締結が必要であるなど、事業場外みなし労働時間の制度を十分理解し、正しく運用するハードルは意外と高いといえます。
営業手当は残業代計算の際には基本給と同じ扱いになりますので、営業職には残業代は必要ないと安易に考えていると思わぬ請求を受けることになります。
③休憩時間があいまい
会社は従業員に、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分、8時間を超える場合少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。
また、この休憩については、一斉付与の原則(従業員に一斉に与える必要があります。ただし、例外あり)と自由利用の原則(自由に使わせる必要があります)が定められています。
従業員が残業代を請求してくる場合、残業代増加の要因になるのが、「休憩時間とされていた時間が実質的には労働時間だった」というものです。
休憩時間は自由に使えなければならないのですが、中小企業の場合、昼食時にスタッフが全員で払ってしまうと電話対応などに困るとして、従業員が会社内で昼食をとりながら、かかってくる電話に対応しているケースがあります。
このようなケースで、会社は「昼食時間に電話に出るのは、そんなに負担ではないはず」と従業員に甘えてしまっていることが多く、従業員と経営者の関係が円満な間は問題が起こりません。また、自席で昼食をとっている最中に、休憩時間だからと言って鳴っている電話には出ないというのも、いかにも融通が利かない感じで、そのような従業員は少数だと思います。
しかし、会社と従業員の関係が悪くなったり、退職してしまったりすると、従業員側は「昼の休憩時間は、電話番をさせられており、法律の言う『休憩時間』として認められない」と主張し、残業代を求めてくることがあります。裁判所も自由利用の原則が認められていない場合、それは休憩時間ではなく、労働時間であると判断される傾向があるので注意が必要です。